
手術までの流れ

手術を安全・安心に受けていただけるようスタッフ全員でサポートします!
-
01
手術決定
-
02
外来
術前検査を行います(血液検査・心電図・呼吸機能など)
-
03
入院
麻酔科医・手術室看護師から麻酔や手術当日の流れを説明します
-
04
手術
病棟看護師・ご家族と一緒に手術室へ行きます

術後疼痛管理チームについて

手術後の「痛み」に特化した専門チームです。医師・看護師・薬剤師で構成しています。
術後、患者さんのベッドに伺い痛みを評価し援します。また、吐き気などの合併症の予防や治療も同時に行っております。
痛みや吐き気などの症状は我慢せず、看護師などのスタッフへお伝え下さい。
手術にあたってのご案内
-
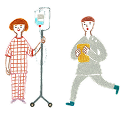
-
ご希望の音楽を手術室で流します!
安心して手術や麻酔を受けて頂くため、可能な限りご希望の音楽を流しています。演歌、最新のJ-POP、洋楽など何でもOKです!スタッフへお申し付けください。
-
アクセサリーなどは外しましょう!
ジェルネイル・時計・指輪・入れ歯などの金属類・コンタクトレンズなどのアクセサリーは外してください。また、髭(ひげ)により呼吸を助けるチューブがずれるため、剃って頂く必要があります。
-
口腔ケアを行い、合併症を予防しましょう!
口腔内には数千億の菌が存在しており、術後の肺炎や傷口の感染に繋がります。グラグラしている歯がある場合は、全身麻酔時に歯が欠けたり、抜けて喉につまる可能性があります。歯や歯ぐきの不安や歯石がある方は、術前にお近くの歯科を受診しましょう!
-
不安なことなど何でもお尋ねください
術前に麻酔科医・看護師が麻酔方法や手術当日の流れをご説明します。また、予定時間を超過した場合、ご家族に経過を簡単にご説明いたします。術後はお部屋まで伺い、お話を伺います。
お気軽にお話ください。
-
-

禁煙、口腔ケア、アクセサリー、内服薬、アレルギーについて
-
1 禁煙について
POINT!
禁煙は、手術の合併症を減らします。術後の肺炎を予防するためには4週間以上の禁煙が効果的です。(数日でも効果あり!)
手術の前は1日でも早く禁煙しましょう!喫煙でおこる合併症
- 脳卒中
- 肺炎
- 傷の治りが遅れる
- 傷が開く
- 傷口の感染
- 骨折
- 骨折の治りが遅くなる
- 死亡率増加
- たんの増加
- 心筋梗塞
- 心不全
- 妊娠や出産への悪影響
- 手術後の痛みも強くなる
禁煙は適切な支援を受けることで成功率が高まります。当院の禁煙外来をご利用ください。
-
2 口腔ケアについて
POINT!
口腔ケアをおこない、口の中の細菌数を減らすことは、術後合併症の危険性を減らします。
歯や歯ぐきの不安や歯石がある方は術前にお近くの歯科を受診しましょう!歯垢1mgに約1 億個の細菌がおり口の中には約4000億個の細菌がいると言われています。
全身麻酔の手術では口からのどの奥を通って肺の近くまで呼吸を助けるチューブが入ります
- 口の中が汚れていると、大量の細菌が気管・肺の奥に押し込まれ、肺炎になる可能性が高まります
- 著しく揺れている歯があると、チューブを入れるときに歯が折れてしまう可能性があります
- そのほかにも、口が原因の合併症はこんなにあります
・誤嚥性肺炎・傷口の感染・心内膜炎・口腔粘膜炎
-
3 アクセサリーについて
POINT!
ジェルネイル・時計・指輪・入れ歯などの金属類・コンタクトレンズなどのアクセサリーは外してください。
また、髭(ひげ)により呼吸を助けるチューブがずれるため、剃って頂く必要があります-
貴金属類は外してください
- ・指輪、ネックレス、ピアス、イヤリング、腕時計、ブレスレット、ベルト、ヘアピンなどは手術前に外してください。
- ・貴金属類を身につけていると、電気メスを使用するときに火傷をする可能性があります。
指輪が抜けない場合は、まず、医師もしくは外来看護師にご相談ください。 - ・手術後は指先がむくみ、指輪の影響で血行障害や神経障害を引き起こす可能性があります。
-
ペースメーカーを使用している方へ
- ・外来/病棟/手術室看護師がお話を伺います。ペースメーカーを使用していることを事前にお知らせください。
- ・手術当日は、ペースメーカーの業者が立ち会います。
(立ち会い同意書にご協力ください。また、ペースメーカー手帳を持参ください。)
-
マニキュア・ペディキュアは落としてください。透明なマニキュアも落としてください
- ・付け爪 (ネイルアート、ジェルネイル等) は、外してください
- ・爪は患者さんの呼吸状態や、種々の身体の状態を知る大切な観察部位となります。
そのため、爪に生体モニターを装着しますが、マニキュアなどを施されていますと評価ができなくなるのでご遠慮ください。 - ・手術前に爪切り、髭剃り、入浴を済ませ清潔にしておきましょう。
-
化粧 (ファンデーション、アイシャドウ、口紅、頬紅、リップクリーム) は落としてください
- ・手術中は患者さんの肌や唇の色を観察します。顔色は呼吸状態や循環動態など患者さんの身体状態を知る大切な観察部位となります。
入室前にすべて落としてください。 - ・肌色を調整する化粧品(BBクリーム、薄付きのファンデーション、パウダー類)もご遠慮ください。
- ・手術中は患者さんの肌や唇の色を観察します。顔色は呼吸状態や循環動態など患者さんの身体状態を知る大切な観察部位となります。
-
眼鏡・コンタクト
- ・コンタクトレンズは、病室で外してください。
- ・眼鏡の必要な方は手術室入室後に外して頂いて構いません。看護師が管理いたします。
-
はずれる歯 (入れ歯、ブリッジ)、ぐらつく歯
- ・全身麻酔で行う手術は、呼吸管理のため口から気管へチューブを入れます。
- ・ぐらつく歯がある場合や入れ歯・ブリッジが入ったままですと、抜けたり外れたりして、気管に詰まる危険性があります。
必ず、麻酔科医・看護師にお知らせください。 - ・矯正中の方はかかりつけの歯科医にご確認ください
-
ヘアピース・かつら
- ・金属で留めるものは、電気メスによる火傷を防ぐために外して頂きます。
- ・金属を使用していないかつらでも、手術に必要な姿勢をとるため、身体を動かす時に頭を支えていた手がずれることで、頭部・頭皮・頚部を痛める可能性があります。
- ・術前訪問もしくは入室時に看護師にお知らせください。髪の長い方は髪を束ねてください。
熱傷や感染などを予防するためにも体につけているものは、すべて外しましょう!
-
-
4 お薬について
POINT!
抗凝固薬は手術中の出血や血栓(血の固まり)を作るため手術前から休薬する必要があります。
サプリメントも含め内服されているお薬をお知らせください!現在内服中(過去1 か月以内に服用したものも含めて)のお薬はもれなくお知らせください。
なお、お薬手帳をお持ちの方は、受診時に必ずご提示ください。-
・お薬によっては手術中に出血が止まらなくなる、逆に血が固まりすぎて血栓を形成するなどの作用を起こし、
非常に危険な状態になる可能性があります。 - ・これらのお薬は、手術の1~2 週間前から中止しなければならないものがあります。
- ・また、麻酔薬を使うと不整脈が出たり、血圧が大きく変動し危険なお薬があります。
- ・術前の中止(休薬)期間中にうっかり、抗凝固剤や抗血小板剤薬を飲んでしまった時には必ずお知らせください。
※抗凝固剤や抗血小板剤(脳梗塞の再発予防薬など)を服用されている方は、出血がコントロールできない危険性があるため、
あらかじめ休薬しなければ、組織生検やポリープ切除を含め、手術ができません。抗血小板剤/抗凝固剤の商品名および成分名の一例 血小板凝集抑制剤 商品名 成分名 バイアスピリン → アスピリン バファリン → アスピリン パナルジン → チクロピジン プレタール → シロスタゾール オパルモン → リマプロスト エパデール → イコサペント酸エチル プラビックス → クロピドグレル エリキュース → アピキサバン 経口抗凝固剤 ワーファリン ワルファリンカリウム 注意事項:
抗血小板作用・抗凝固作用のある薬剤は、上記の商品名以外にも多くのものが流通しております。
糖尿病薬、経口避妊薬などのお薬も、お申し出ください。
術前のお薬の中止(休薬)、および再開は医師の指示に従ってください。 -
・お薬によっては手術中に出血が止まらなくなる、逆に血が固まりすぎて血栓を形成するなどの作用を起こし、
-
5 アレルギーについて
POINT!
手術室では特殊な薬剤や物品を使用します。関係なさそうな食べ物でも手術室では貴重な情報です!
アレルギーがある場合はお知らせください!手術室では消毒薬やテープ、特殊な薬剤などを多数使用します。
アレルギーがある場合、危機的な状態になる可能性もあります。
そのため、関係する薬剤や物品を使用せずに麻酔や手術を行います。
安全に手術を受けて頂くためにスタッフヘお知らせください。-
代表的なアレルギー
- ・消毒液(アルコール・イソジン)
- ・ゴム製品
- ・テープ(湿布など)
- ・金属
- ・薬剤(抗生剤・造影剤など)
- ・果物(食べた時、「喉のかゆみ」や「イガイガ感」がある場合もアレルギーです!)
-
-
-

麻酔説明、食事・水分の制限、保護者の付きそいについて
-
1 麻酔説明(術前訪問)
POINT!
手術・麻酔について気になることや不安なことなど、遠慮なく何でもお話ください!
手術を安心して受けて頂けるよう手術室スタッフ全員でサポートいたします!手術の前日、または当日に麻酔科医師から麻酔の方法や合併症についてご説明いたします。
また、手術室看護師より手術当日の流れや手術体位などをお話しします。
手術・麻酔について気になることや不安なことなど、何でもお話ください。詳しい麻酔方法については、「6.麻酔方法の種類」をご覧ください。
説明の主な内容
-
- 麻酔科医師
- 麻酔方法、麻酔の合併症について、麻酔歴・手術歴・既往歴
- 手術室看護師
- 手術全体の流れ、手術室内のBGM の希望、手術体位、アレルギーについて
-
-
2 食事・水分の制限(絶飲食について)
POINT!
水分をとることで脱水を予防し安全に手術を受けることができます。
しかし、絶飲食が守られない場合、手術の延期や麻酔方法を変更することがあります。絶飲食時間は必ず守りましょう!麻酔中に嘔吐し、食べ物や飲物が肺に入ると窒息や肺炎になる可能性があります。
そのため、手術当日は食事・水分を中止し麻酔や手術を安全に受けて頂きます。
消化時間が違うため食べ物から先に中止し、最終的に水分も飲めません。
水分が飲める時間は、水分をこまめにとりましょう!(スポーツ飲料や水や果汁が入っていないジュースはOK!)基本的な絶飲食時間
- 食事 手術前8時間
- 水分 手術前2時間
患者さんの状態によって絶飲食時間は変わります。
医師の指示のもと、病棟看護師から絶飲食時間をご説明いたします。
付き添われるご家族への情報共有もお願いいたします。 -
3 保護者同伴入室(ご家族1 名まで入室可能)
POINT!
全身麻酔で眠られるまで、お子様と一緒に手術室へ入ることができます!
お子様の不安を少しでも緩和できるようにぜひご入室ください!当院では、お子様の手術に際し、保護者の方と一緒に手術室へ入室することが可能です。※保護者1 名まで
お子様の不安を少しでも緩和できるよう、保護者同伴入室をお進めいたします。保護者同伴入室の流れ
-
01
お子様と一緒に保護者1 名入室
-
02
医療機器をお子様につけます
-
03
名前や生年月日などの確認
-
04
全身麻酔
-
05
保護者の退室(看護師がご案内します)
-
-
-

-
POINT!
手術室のスタッフがずっとそばにいます。
何でもお話しください!手術室での全体の流れ
-
01
手術室へ入室
お名前・生年月日を確認します
-
02
器械の装着
血圧計や心電図などを装着します
-
03
安全確認
術式や同意書、アレルギーなどの確認を行います
-
04
麻酔開始
全身麻酔、局所麻酔を行います
-
05
手術
外科系医師が手術を行います
-
06
手術室退室
麻酔から覚醒し退室します。酸素マスクをはめます
-
-
-

食事・水分の制限、痛み止め、合併症について
-
1 食事・水分の制限
POINT!
全身麻酔により嚥下機能が低下しているため、誤嚥性肺炎などの合併症を起こす可能性があります。
許可がでた後も、飲み込めない場合や気分が悪い場合はスタッフへお知らせください!全身麻酔により嚥下機能が低下しているため、誤嚥性肺炎などの合併症を起こす可能性があります。
そのため、術後の状態や手術、麻酔方法により食事・水分を開始する時間が異なります。
消化器の手術などは数日の間、絶飲食が続く場合もあります。
食事や水分の許可は、医師の指示のもと病棟看護師から説明いたします。手術の方法や麻酔方法によって食事・水分の開始時間が変わります
-
2 痛み止めについて
POINT!
痛みは頭痛や吐き気など合併症を引き起こす可能性があります。また、鎮痛剤が効くまでに時間がかかります。
早めにスタッフへ相談し、鎮痛剤を使いましょう!鎮痛剤の種類と効果
-
内服薬
徐々に痛みが取れ、長時間効きます。 注意:術後飲水出来ることが条件です
-
点滴
一番早く効果が現れますが、持続時間は長くありません。 注意:薬によっては、呼吸があさくなる場合があります 。また、血圧が下がることがあります
-
座薬
約30 分程で痛みが取れ長時間効きます。 注意:血圧が下がることがあります
-
硬膜外麻酔(PCA ポンプ)
背中に入っているチューブから痛み止めが持続的に流れます。
痛い時にタンクのボタンを押すと3ml薬が流れます。
30 分でタンクに薬が補充されます。
術中に行う麻酔です。麻酔科医が行います。 注意:血圧が下がることがあります。薬が効きすぎて足が動かなくなる場合があります
-
-
3 合併症について
POINT!
術前の禁煙や口腔ケア、術後の早期離床などにより合併症を予防できます!
合併症を防ぐことで、術後回復能力を向上させます。合併症を予防し早期に回復しましょう!手術や麻酔、術後の安静などにより合併症を起こす可能性があります。
合併症の予防や早期に回復できるよう、サポートいたします。主な術後合併症
-
吐き気
手術患者の30%が起こると言われています。
薬を使用し症状を改善することができます。 -
筋力低下
ベッド上で安静にしていることで、筋力が著しく低下します。
ベッド上でのリハビリや歩くなど、早期に離床することが効果的です。 -
肺炎
むせて水分や食べ物が肺に入る際や喫煙などにより呼吸機能が低下している場合に起こります。
禁煙や口腔ケアを行うことで予防できます。 -
せん妄
注意力障害・認知機能障害のことをさし、高齢者の10~40%で発症すると言われています。
日常生活に近い環境にすることで予防できます
-
-
-

全身麻酔、局所麻酔について
手術をする前に必ず麻酔を行います。麻酔は大きく2 つに分かれます
麻酔科医が、患者の状態や手術の内容を考えて麻酔方法を決定します。
2 つの麻酔を併用する場合もあります。-
- 全身麻酔
- 眠るため手術中の記憶はありません
- 局所麻酔
- 起きていますが、痛みは感じません
・硬膜外麻酔・脊椎くも膜下麻酔・末梢神経ブロック
-
1 麻酔の特徴と方法
全身麻酔
- 特徴
- 手術のあいだ眠っている麻酔です
- 方法
- ①マスクから酸素を吸います
- ②点滴から眠る薬を入れます
-
③呼吸を助けるチューブを口から入れ、
人工呼吸器を使って呼吸します
- 注意点
- 心臓や肺に負担がかかる麻酔です
硬膜外麻酔
- 特徴
- 痛み止めを数日間、持続的に投与するため、
術後の痛みを和らげます - 方法
- ①横向きになって背中を丸めます
- ②局所麻酔を背中にします
-
③体の中に細いチューブを入れテープで
固定します
- 注意点
- 下肢のしびれや足が動かない場合は
お知らせください
脊椎くも膜下麻酔
- 特徴
- 数時間、下半身が麻痺し痛みを感じません
- 方法
- ①横向きになって背中を丸めます
- ②局所麻酔を背中にします
- ③麻酔薬を体の中に入れます
- 注意点
- 気分が優れない場合や呼吸が苦しい場合は
お知らせください
末梢神経ブロック
- 特徴
- 手足やお腹の神経を麻痺させる麻酔です。
持続時間が長いため、術後の痛みを緩和することもできます。 - 方法
- ①エコーを使って神経が走行している層を見ます
- ②神経の周りに局所麻酔薬を注射します
- 注意点
- しびれが長時間とれない際はお知らせください
-
2 麻酔の組み合わせの例
POINT!
麻酔は手術を安全・安心に行うために必要不可欠です。術中だけでなく術後の痛みも和らぐよう、麻酔方法を併用します。
一つ一つ丁寧に説明しながら麻酔を行いますのでご安心ください!!お腹の手術
全身麻酔+硬膜外麻酔
全身麻酔+末梢神経ブロック足や下腹部の手術
脊椎くも膜下麻酔
帝王切開
硬膜外麻酔+脊椎くも膜下麻酔
手や腕の手術
全身麻酔+末梢神経ブロック
頭の手術
全身麻酔+局所麻酔
※手術や患者さんの状態によって麻酔方法を考えて組み合わせます
麻酔についての詳細は、麻酔科医が手術前に必ずご説明いたします
麻酔についての質問や不安など、何でもお話しできますのでご安心下さい
-
-

手術は人生の中でも大きなイベントです。
想像がつかず漠然とした不安を抱えていらっしゃると思います。
皆様が安全・安心に手術を受けて頂けるよう医師、看護師、臨床工学技士など
多職種のスタッフが一丸となって皆様をサポートいたします!
